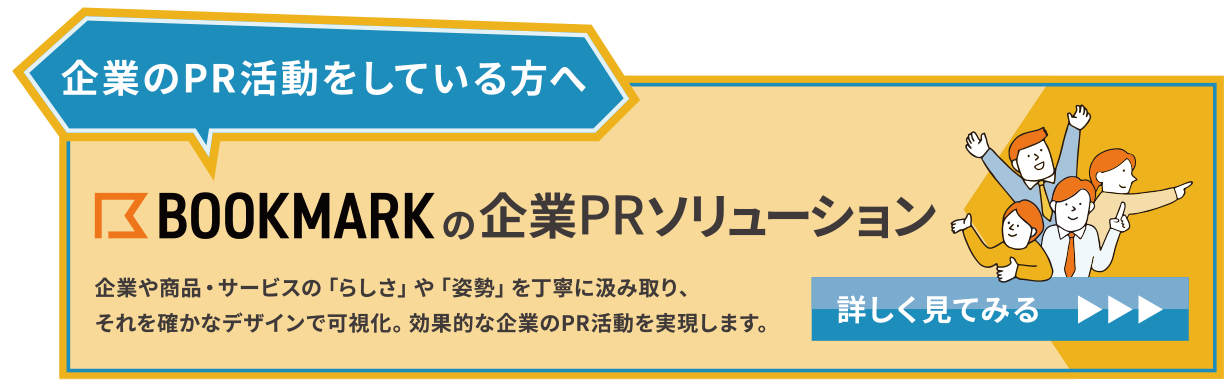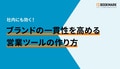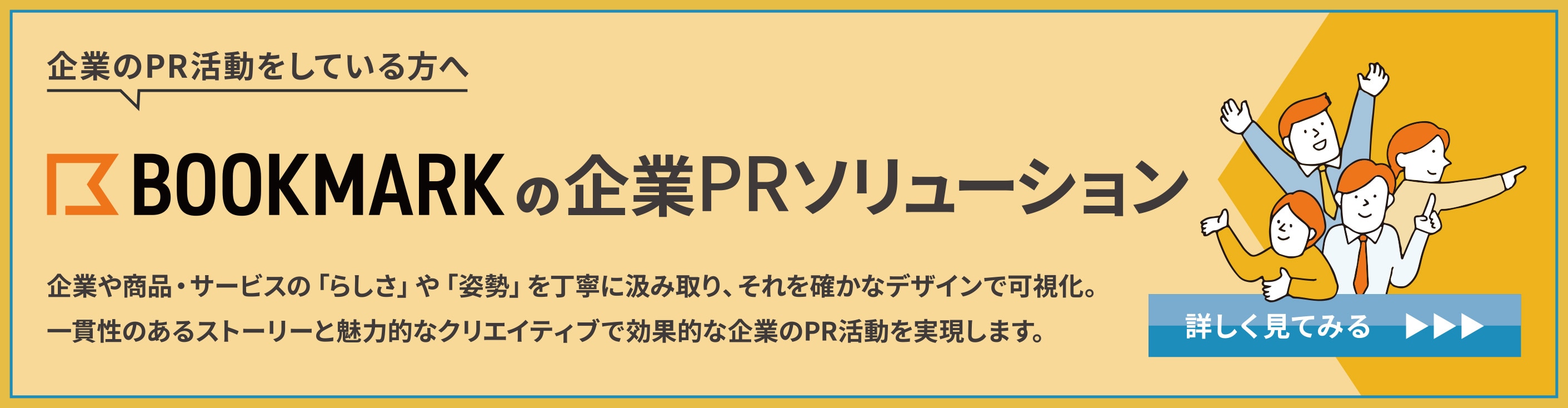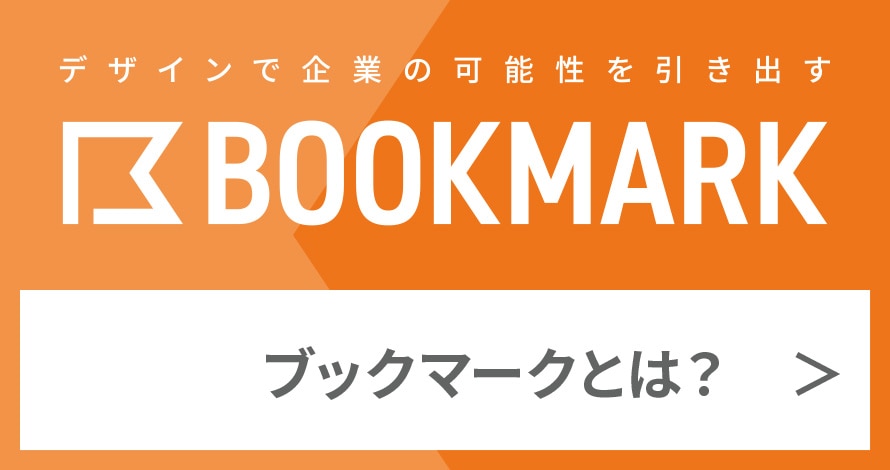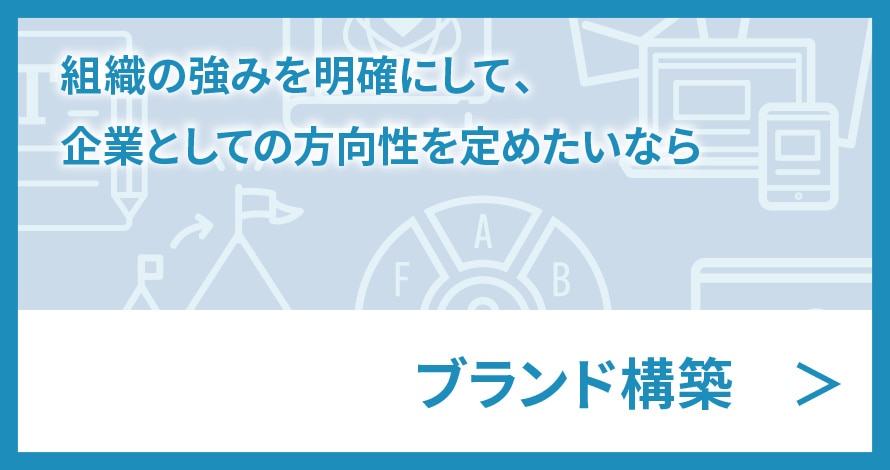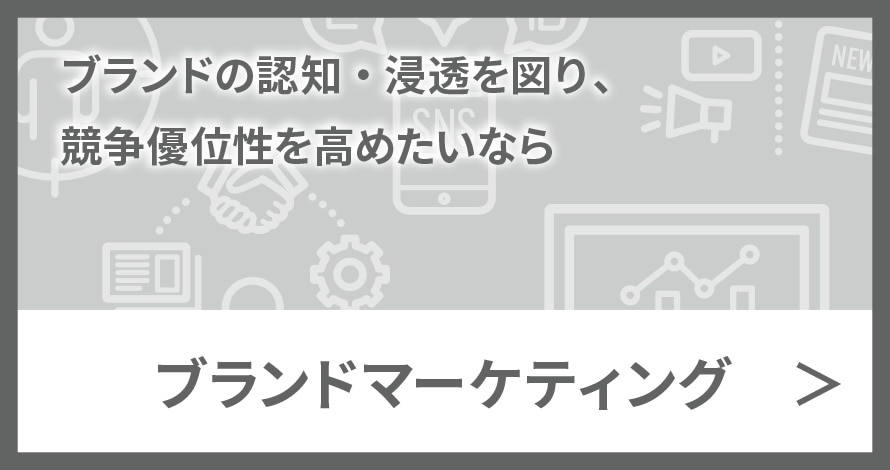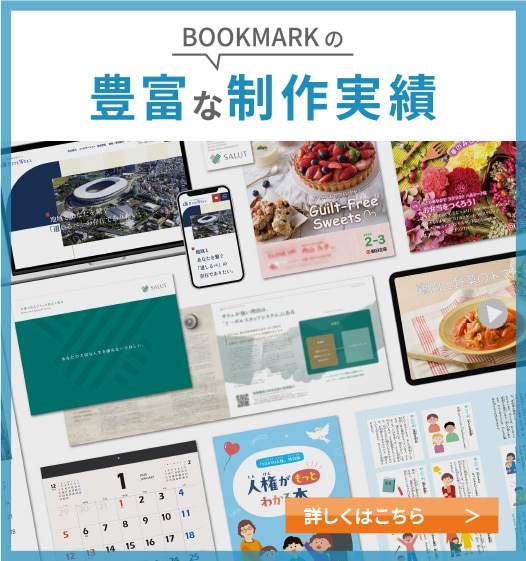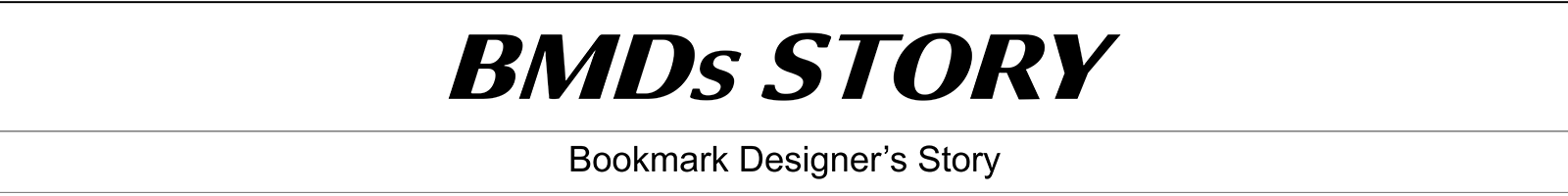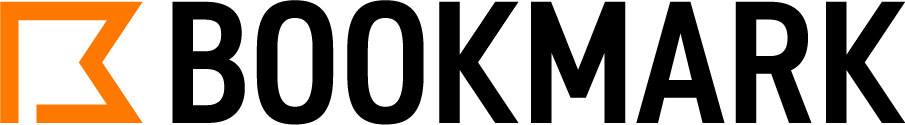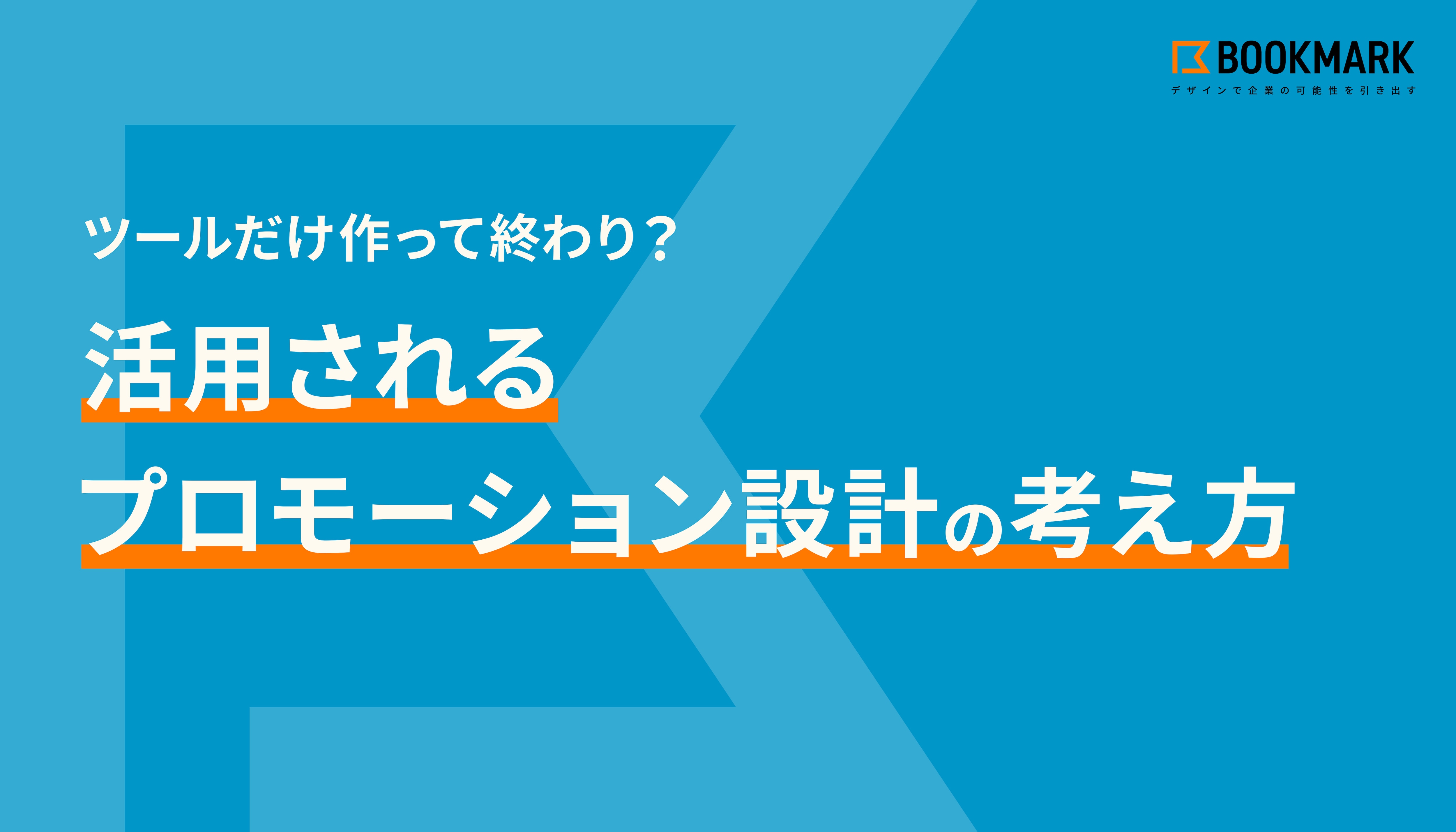
ツールだけ作って終わり?活用されるプロモーション設計の考え方
「ツールを作ったのに、ぜんぜん使われていない……」そんな経験はありませんか?
プロモーションツールは、単なる制作物ではなく、戦略的に活用してこそ意味があるものです。
配って終わり、置いて終わりでは、お客さまの心にも届きません。
この記事では、プロモーションツールが「活用される」状態をどう設計するかをテーマに、販促施策との連動や社内外での運用視点から、具体的な考え方をお伝えします。
目次[非表示]
なぜ「作って終わり」になるのか?
プロモーションツールの多くは、制作段階での目的設計が曖昧なまま進みがちです。
・誰に向けて、どう使うのかが明確でない
・社内での展開ルートが整っていない
・営業や現場と連携せず制作されている
その結果、「とりあえず印刷して配布しているが、反応がない」「営業の現場では使われていない」といった状況に陥ってしまいます。
プロモーションツールは“活用設計”がすべて
プロモーションツールを活かすには、活用設計=どこで・誰が・どう使うかの導線設計が欠かせません。
目的と活用シーンを明確にする
・展示会での集客?
・商談の補助?
・Webからの資料請求対応?
・社内トレーニングや説明用?
など、シーンごとに「活用される状況」を具体化することが第一歩です。
社内共有・活用フローの設計
・営業やカスタマー部門にどのように届け、どう使ってもらうか?
・説明方法や活用タイミングは統一されているか?
・社内の誰が管理、改善の責任を持つのか?
ツールは“使う人”に届いてはじめて効果を発揮します。社内への「伝達」も設計の一部です。
Web・動画・イベントとの連動
印刷物単体ではなく、
・Webサイトの資料請求フォームと連携
・動画とQRコードでクロスメディア展開
・イベントやセミナーでの回収導線設計 など、他チャネルと連動してはじめて、反応が取れるツールになります。
ツール活用の工夫:事例に学ぶ
例1:展示会での配布だけでなく“次アクション”につなげる
・製品パンフレットにQRコードを設置し、フォーム誘導
・フォロー営業用に「興味レベル別」の補足資料を用意
・名刺交換後に自動で届くお礼メールとツールPDF
例2:営業現場での“説明ツール”として活用
・営業の話法に合わせた構成(ストーリー設計)
・相手の業種に合わせてセレクトできるパーツ構成
・紙とPDFで併用できるマルチフォーマット展開
例3:社内での理解促進にも活かす
・新サービス説明パンフを社内研修資料として活用
・ツールに込めた意図をイントラで共有
・トーク例や想定Q&Aを含めたガイド付き仕様
まとめ:プロモーションツールは「使われてこそ価値」
ツールの良し悪しは、デザインや紙質だけでは測れません。
「現場でどう使われ、効果につながっているか」こそが本質的な評価軸です。
・目的と活用シーンを明確に
・社内展開と共有フローまで設計
・Webや動画との連動も意識
制作前から“活用される未来”を見据えて、プロモーションツールを戦略的に活かしていきましょう。