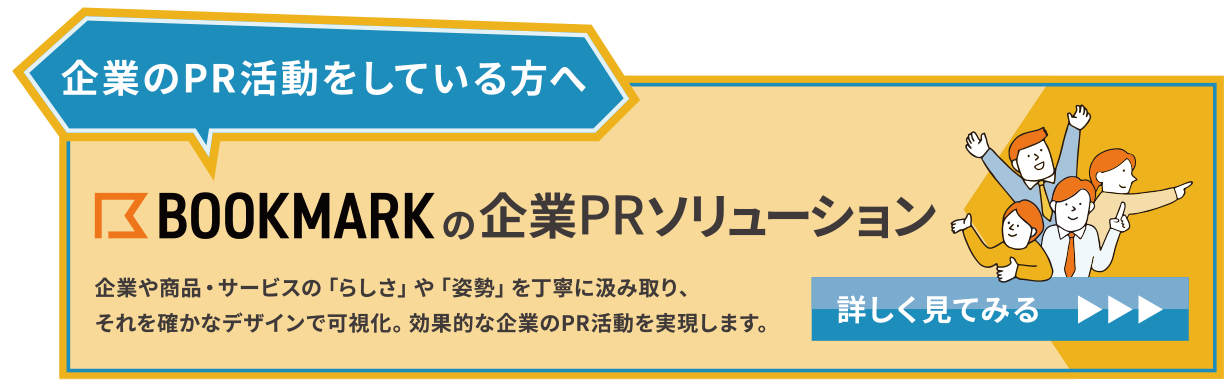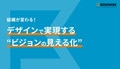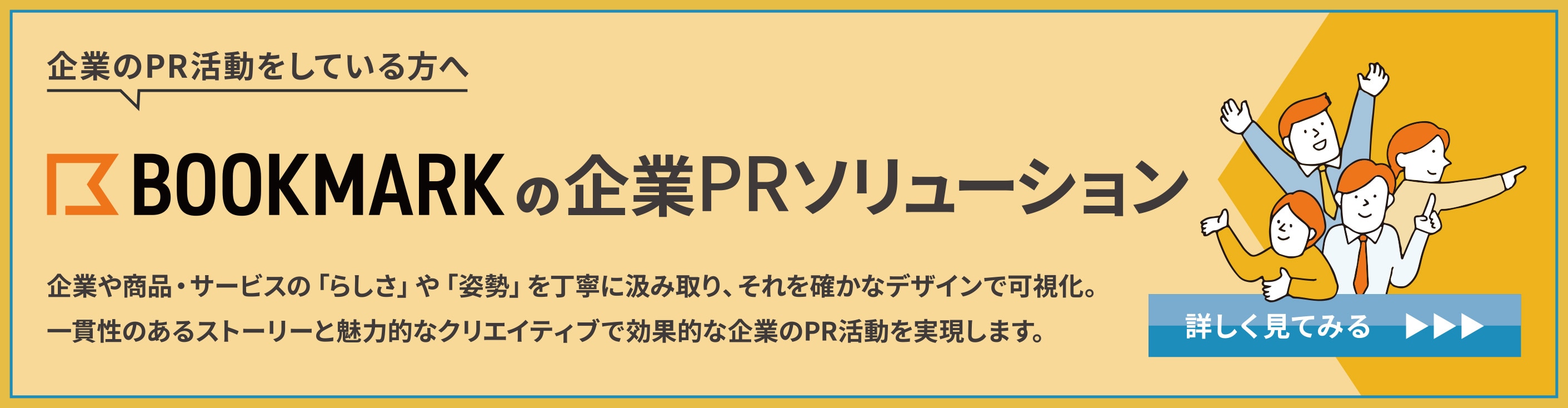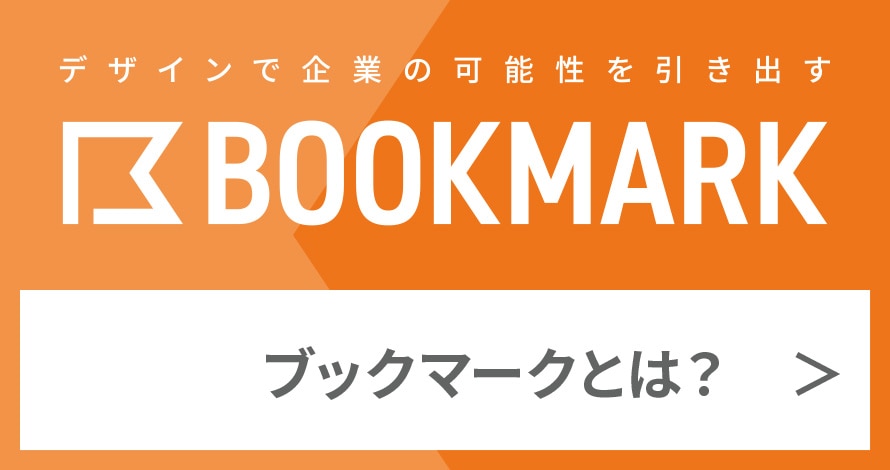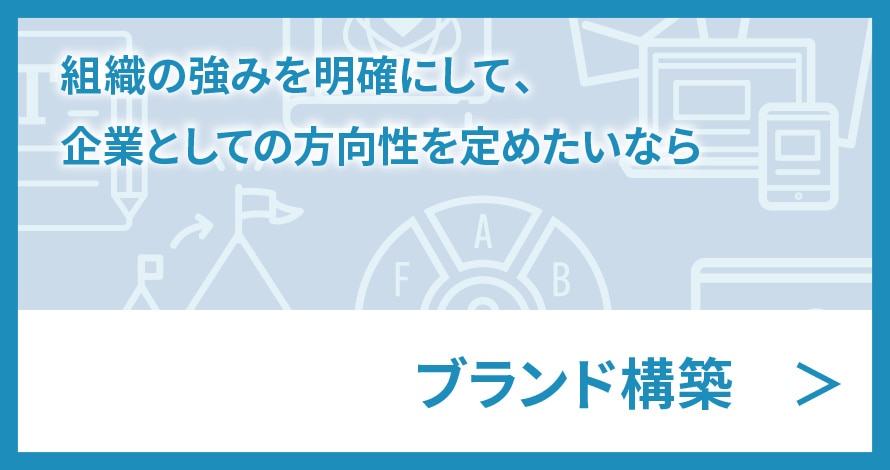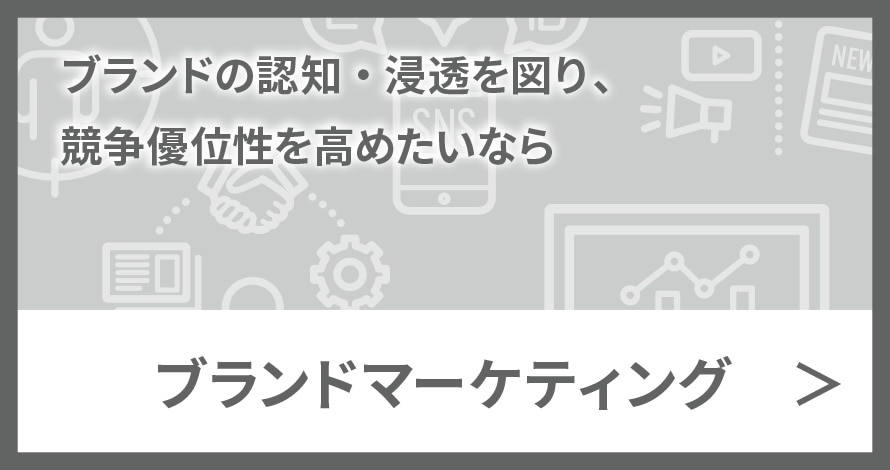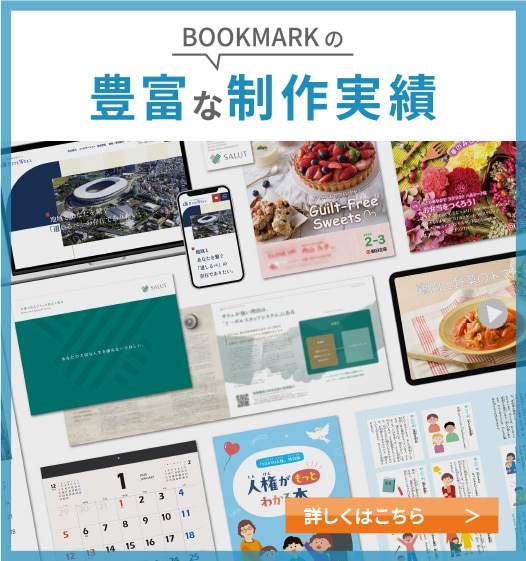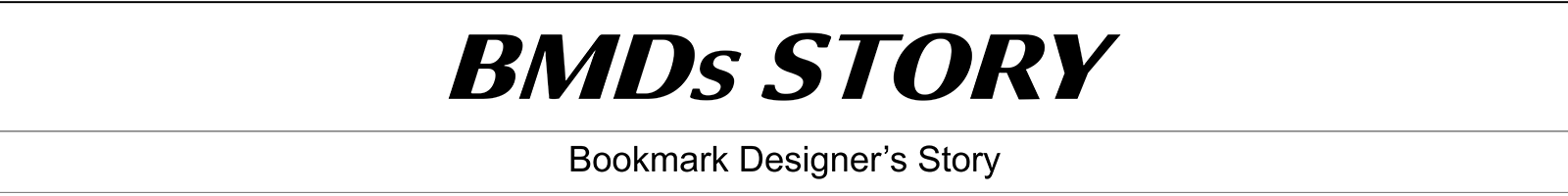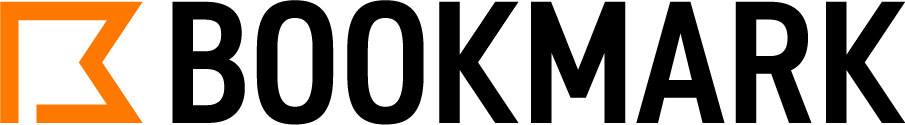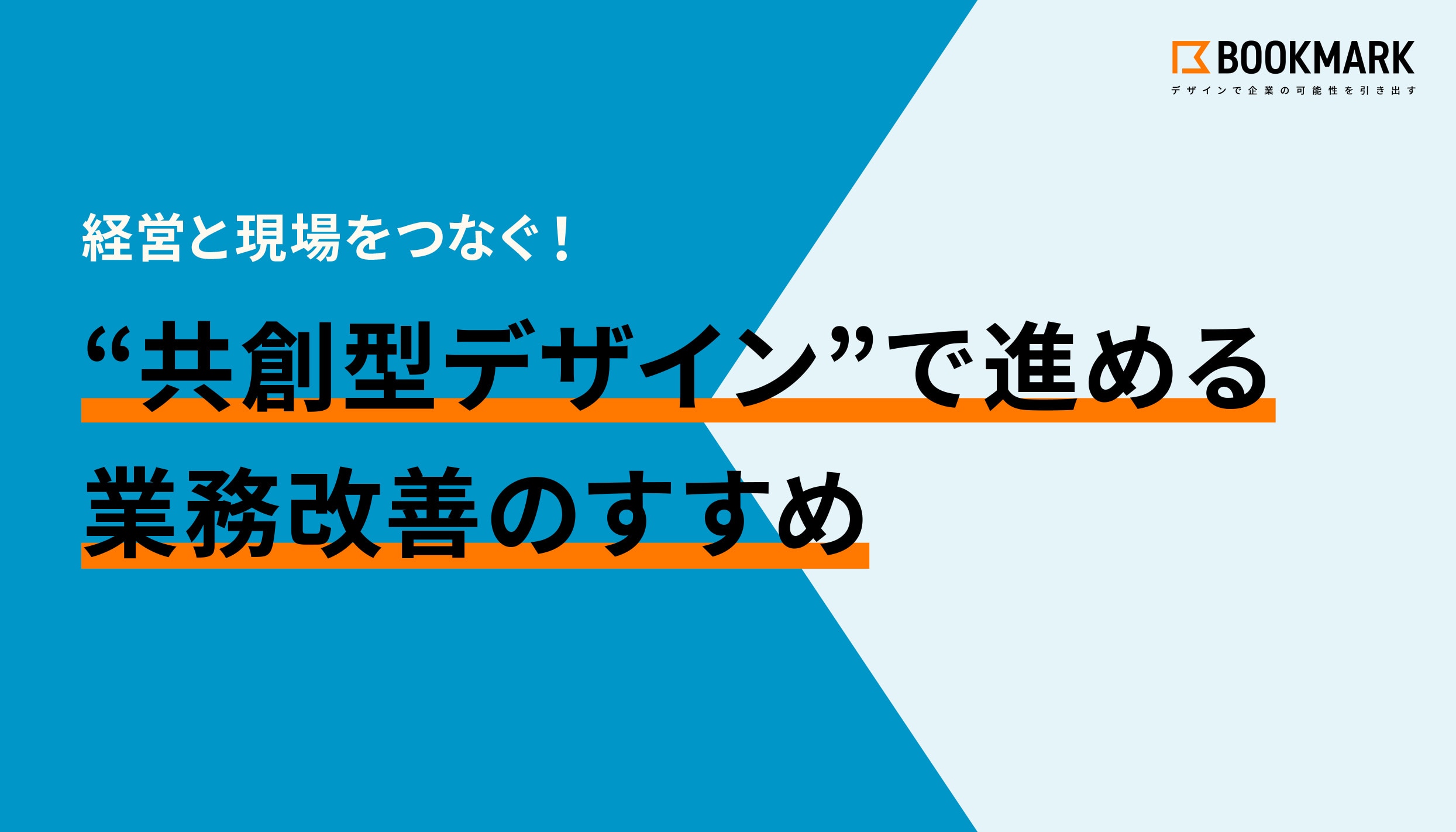
経営と現場をつなぐ!“共創型デザイン”で進める業務改善のすすめ
現場と経営、分断していませんか?
「現場の声が経営に届かない」「トップの意図が現場で形にならない」
そんな“すれ違い”が積み重なると、組織の改善活動は形骸化してしまいます。
そこで注目されているのが、“共創型デザイン”という考え方。
経営層と現場が対話しながら、課題を可視化し、理想の業務プロセスを共に設計する手法です。
目次[非表示]
- 1.共創型デザインとは?
- 2.なぜ今、共創型デザインなのか?
- 2.1.“属人化”の限界がきている
- 2.2.デジタルツールの導入が進む中で「使いにくさ」が課題
- 2.3.「やらされ感」では改善は進まない
- 3.共創型デザインによる業務改善のプロセス例
- 3.1.業務ヒアリングと課題抽出
- 3.2.情報構造・業務フローの再設計
- 3.3.改善案を“見えるカタチ”にする
- 3.4.定着支援と運用改善
- 4.導入事例:こんな組織が変わった!
- 5.まとめ:デザインは現場と経営をつなぐ“共通言語”になる
共創型デザインとは?
共創型デザイン(Co-Creation Design)とは、デザインのプロセスを通じて多様なステークホルダーが課題を共有し、解決策を“共に考え、共につくる”アプローチです。
単なる「おしゃれなデザイン」ではなく、
・情報設計
・業務フローの可視化
・UI/UXの改善
といった実務に根ざした仕組みづくりにデザインの力を使います。
なぜ今、共創型デザインなのか?
“属人化”の限界がきている
ベテラン社員の経験値に頼った業務は、ブラックボックス化しやすい。可視化と共有で、誰でも再現可能な仕組みにする必要があります。
デジタルツールの導入が進む中で「使いにくさ」が課題
せっかくのツールも、現場の流れに合っていなければ定着しません。業務目線で設計されたUI・フローが求められます。
「やらされ感」では改善は進まない
経営からのトップダウンだけでは限界があり、現場が納得して動ける仕組みこそが、改善の原動力になります。
共創型デザインによる業務改善のプロセス例
業務ヒアリングと課題抽出
・現場メンバーと対話しながら、実際の流れをヒアリング
・“ボトルネック”や“非効率ポイント”を洗い出す
・感覚ではなく、見える言葉と図解で課題を可視化
情報構造・業務フローの再設計
・複雑なプロセスをシンプルなステップに再構築
・誰が、いつ、何を、どう判断するかを整理
・必要に応じて、帳票、画面、導線も再デザイン
改善案を“見えるカタチ”にする
・ワイヤーフレーム、プロトタイプ、業務マニュアル、動画などで共有
・現場の声を取り入れながらブラッシュアップ
・“説明不要”で直感的に理解できるアウトプットに
定着支援と運用改善
・実装後も、運用状況をチェックして改善を継続
・「仕組みがあるのに使われない」を防ぐために、デザイン×仕組み×習慣づけを一体で設計
導入事例:こんな組織が変わった!
・製造業A社:紙のチェックリストをデジタル化し、工程ミスが1/4に
・教育業B社:先生の業務フローを見直し、事務作業時間を40%削減
・自治体C庁:住民対応マニュアルを図解し、職員の対応品質が安定
まとめ:デザインは現場と経営をつなぐ“共通言語”になる
デザインとは、ただの見た目ではなく“伝わる仕組み”をつくる力。
経営の想いを現場に届け、現場の声を経営に返す——
その橋渡しをするのが、共創型デザインの役割です。
これからの業務改善には、共創・可視化・納得感のあるプロセス設計が欠かせません。
そして、それを実現する最強のツールが“デザイン”なのです。